取手駅前開発と図書館を考える
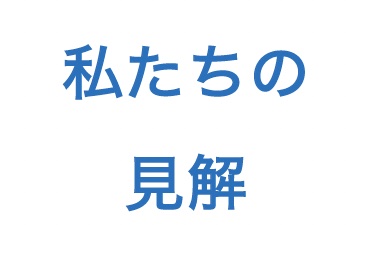
「駅前開発を考える会」代表 遠藤俊夫
この意見は「明るい取手」(日本共産党取手市委員会の広報誌)の2023年7月21日号から2025年1月19日号に連載されました。日本共産党取手市委員会のご了承を頂き、ここに転載します。
1)「請願」(註)して感じたこと、考えたこと
請願権とは、国や地方公共団体の機関に対して、その職務に関する事項についての希望・苦情・要請を申し立てる、憲法第16条で認められた権利です。私たちはこれまでも取手市議会へいくつもの請願をしてきましたが、今回は議会だけではなく、図書館の移転問題でもあるので、図書館を所管する「教育委員会」にも取手市教育委員会会議規則第10条(請願)の規定に基づき、請願しました。教育委員会への請願には、議会と違って、気を遣う例のやっかいな「紹介議員」は不要なので、もっと気楽に請願することができるので皆さんにお勧めします。
結果は、議会・教育委員会いずれも「不採択」でした。これまでも何度も経験しているので、「不採択」には驚きませんが、請願に込めた「希望・苦情・要請」に対して、議会・教育委員会が全く不誠実であるばかりか、その見識の欠如にあきれるばかりでした。
(註)この「請願」は、取手市が2024年3月15日の市報で突然発表した「取手駅西口駅前に『図書館を核とした複合公共施設』の整備を目指します!」の構想に対し、「考える会」が市議会に対して行った2件の請願と、教育委員会に対して行った1件の請願を指します。詳しい経緯はこのホームページ内の「会発足からの主立った活動」【こちら】の5月24日〜7月5日の記事とリンクをご参照下さい。
2)社会教育はぜいたく品か?
『学習権宣言』(1985年ユネスコ国際成人教育会議採択)は、「学習権は・・・未来のためにとっておかれる文化的ぜいたく品ではない」、「人間の生存にとって不可欠な手段」であり、「より健康な生活を営む」ために、そして「戦争を避ける」ために、「平和に生きることを学び、お互いに理解しあうことを学ばねばならない。」 学習は、「人々を、なりゆきまかせの客体から、自らの歴史をつくる主体にかえていくものである。」 学習権は基本的権利の一つであると述べています。
我が国の社会教育法では、社会教育は「すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高める」活動であり、市町村に、公民館や図書館など社会教育施設の設置を奨励し、社会教育の振興を義務づけています。憲法第26条(教育を受ける権利)と共鳴しています。
二人の含蓄のある言葉を紹介します。ジャーナリストの武野武治は「学ぶことをやめれば、人間であることをやめる。生きることは学ぶこと、学ぶことは育つことである」(『詞集たいまつ』)。詩人の岡部伊都子は「もう八十過ぎのおばんは、若さから解放されているんや、だから人間として、さらに解放されたい。・・・死ぬまで、自分を育て、解放されなければ。新しい自分を生んでいる。すごい、すてきなことやな」(『遺言のつもりでー伊都子一生語り下ろし』)。
3)図書館は「まちの魅力」の大きな要素
前回2)では、私たちが日々暮らしていくうえで図書館や公民館などがいかに大切な施設であるかということを述べました。同時に図書館などは、この街にずっと住み続けたいと思わせる―特に若い子育て世帯にとっては—「まちの魅力」の一つの大きな要素ではないでしょうか。
調布市図書館は、「買い物かごを下げて図書館へ」「“日本一”役立つ・満足できる図書館に!」をキャッチフレーズに、歩いて10分で利用できる、800mに一つ、人口2万人に一つ、小学校区に2つ、という「いつでも どこでも だれでも」利用できる図書館網(本館・分館)を作っています。図書館は、「利用者があらゆる種類の知識や情報をたやすく入手できる地域の情報センター」(ユネスコ公共図書館宣言2022)です。読書に応えるだけではなく、職を求める人、悩みや解決したい課題を抱える人などにも適切な情報を提供できる、相談業務を含めた図書館サービスが求められています。取手市に住んでみたい人が増えれば、駅前も賑わうのではないでしょうか。
4)思いがけない本との出会いの場、未知の世界へ開かれる場、それが図書館の輝き
バードウォッチングのために野鳥図鑑を見に来た利用者が、冒険小説のような題名に惹かれて思わず手に取った『ソロモンの指環』というタイトルの本、それが動物行動学の古典的な名著(コンラート・ローレンツ著/日高敏隆訳/早川書房)だった。また、ここ数年、新着図書コーナーには「ウクライナ」や「プーチン」という文字を冠した本が目立っているが、新刊書はまさに時代や社会を映す鏡です。これらを読むことで未知の世界に目を開かれ、自分の考えを深めたり、独自の判断や意見をもつことができます、と(元町田市立図書館長守谷氏が雑誌『月刊社会養育』(2024.4)に寄せた小論)。さらに、氏は「図書館は、自らの生活を豊かに、また合理的にしようとする市民を、手助けする仕事であり、主権者としての市民が自ら考え行動することをサポートすることであり、自治体行政を支える基盤となるものだ」とも述べています。取手市は図書館づくりを安直に考えてはいけないよと“警告”しているような気がします。
5)図書館ボランティアに支えられて
取手図書館とふじしろ図書館には大勢の市民が、図書館ボランティアとして図書館を支えています。①乳幼児から小学生ぐらいの子供たちに、絵本の読み聞かせ・おはなし=ストーリーテリング・布絵本づくりで本に親しんでもらう活動、②点訳・朗読資料づくり、③返却本の補修・配架、④環境整備(草取り等)等など。また彼らは各活動分野ごとにサークルをつくり仲間の親睦を図ったり独自活動(例えば、乳児検診時に呼ばれて絵本の読み聞かせをする)などをしています。文科省も「図書館におけるボランティア活動が、住民等が学習の成果を活用する場であるとともに、図書館サービスの充実にも資するものであることにかんがみ、・・・多様なボランティア活動等の機会や場所を提供するよう努めるものとする。」(『図書館の設置及び運営上の望ましい基準』)と指摘しています。図書館移設計画づくりには当然、活動するボランティアの声にも真剣に耳を傾けることが求められているのではないでしょうか。
6)図書館の“新しい”役割と「図書館はなぜ無料なのか?」を学ぶ
先日開いた図書館問題学習会で取手図書館員から教えられました。図書館の役割は従来、図書等資料を提供して住民の個人的な学習を支援することだったが、近年は、地域が抱える課題(就業・子育て・教育・健康・医療・法律・政策決定等)の解決に役立つための情報提供サービスが求められていると言います。たしかに市内には、高齢者、貧困・ヤングケアラー、非正規労働者、外国人、障がい者等多様な市民がいます。それぞれが抱える課題に向き合って、適切な情報を届ける仕事は益々重要で、公共図書館だからこそできる仕事でもあります。「駅前の賑わいを取りもどすため」の図書館移設計画構想にはこうした視点があるのでしょうか。
「図書館がなぜ無料なのか?」、それは、求められている新しい役割を果たすのが公共図書館だからこそ無料だと、そして「図書館サービスから受ける利益は、その利用者だけにもたらされるのではなく、図書館で読んだり、情報を得て活動する市民が増えて、社会全体(つまり取手市)が成熟することが期待されるから、だから無料なのだと。明解ですね。
7)図書館運営を民間委託(指定管理者)から直営にもどした守谷市中央図書館
2016年度から、民間業者(指定管理者)に委託して運営されていた守谷中央図書館は、2019年4月から市直営に戻った。「守谷の図書館を考える会」の地道な活動が、市民を動かし、市議会を変えたのだ。取手市より人口は少ないが、市の図書館への思い入れは注目に値する。図書館統計を見ていただくと一目瞭然だ。人口一人当たりの資料費(図書購入費)は527円と抜きんでて高い。比べて、取手市の図書館予算の減少が気になる。
「駅前の賑わいを取り戻すために取手図書館を廃して駅前に移転する」構想に見られる哲学・理念の貧困は、取手市民にとって誠に不幸なことだ。「図書館で読んだり、情報を得て活動する市民が増えて、社会全体が成熟」することこそ、取手市の発展につながるのではないのか。取手市は図書館をもっと大切にしてもらいたいものだ。
図書館統計資料(『茨城の図書館』より)

(シリーズ「駅前開発と図書館と考える」は今回で終ります。遠藤俊夫)
