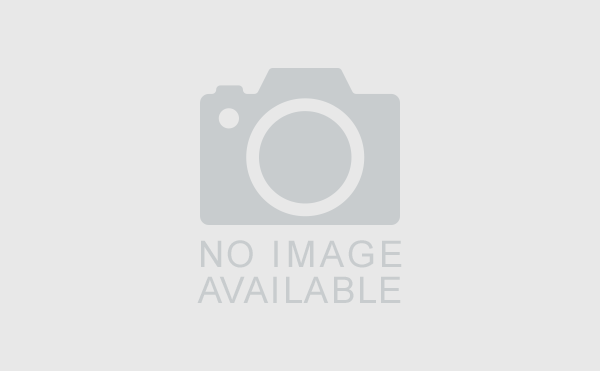10.24 図書館学習会報告

10月24日(木)、取手福祉会館3階・会議室Eにて、取手図書館係長に講師をお願いし、第一回「図書館問題を考える学習会」を開催しました。会には20名を超える参加者があり、質疑も活発で、図書館への理解を深めることができました。図書館が「タダの貸本屋」や「本が読める娯楽施設」でないことが良く分かりました(私たち「考える会」のメンバーにも嘗てそう考えていた人がいました)。
事前にお願いしていた、①図書館の役割、②なぜ無料で利用できるのか、の二点について、以下の解説を頂きました。
①図書館ってどんなところ?
・図書館とは、図書、記録その他必要な資料(いろいろな種類がある)を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクレーション等に資することを目的(図書館法第二条抜粋)とした活動をするところです(太字を重視)。
・具体的な機能には、資料の収集、整理、保存、貸出、レファレンス(調べもののプロである図書館司書が、利用者の調べものの支援をすること)、課題解決のための情報の整備・提供、などがあります。これらを通じて個人の生涯学習を支援します。近年要望が高まっている「課題解決支援」には、子育て支援(ブックスタート支援)、学校支援、多文化支援、ビジネス支援、行政支援などがあります。
・図書館は、「地域の知の拠点」として国民の生涯にわたる自主的な学習活動を支え、促進する役割を果たす場所であり、地域が抱える様々な課題解決の支援や、地域の実情に応じた情報サービスなど幅広い観点から社会貢献する場所であることを期待されている、と考えています。
スマホが普及し、検索機能が充実してきたことにより、自分で問題設定をしたり、図書館で調べたりすることを面倒と考える風潮が広がっていますが、誰でも無料で利用できる図書館を活用し、自分の世界を広げて頂きたいと思います。
②図書館はなぜ無料なのか?
・図書館法第十七条で「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない」と定められています。その理由として、「貧富の差で(利用の)制約を受けてはならない」(文部省社会教育局長 西崎恵)から、と説明されています。
・今の公立図書館の在り方は占領下に形作られ、アメリカに倣って無料とされました。1950年代には改正論がありましたが、1960年代には無料で定着しました。1990年代から、電子化、緊縮財政、多様なサービス要求などに対応するため、再び「有料化」(一部有料化も含む)の意見が出ています。
・しかし、「図書館サービスの益は、その利用者だけにもたらされるのではなく、図書館で読んだり、情報を得て活動する住民が増えるほど、社会全体が成熟することが期待される」、だから無料で良い、と考えることができると思います。
以上が頂いた解説の概略です。
図書館が無料であることの受益者は「社会全体」と言う指摘は重要です。本来、図書館ばかりでなく、一般に、教育の受益者は日本社会、日本国であり、教育を受ける権利が貧富の差で差別を受けてはならない、と、私たちも思います。
解説の中で、図書館の関係法令の一つとして「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」の紹介があり、その「第一、三、運営の基本」の⑤に次の条文があることを知りました:
「図書館の設置者は、当該図書館の管理を他の者に行わせる場合には、 当該図書館の事業の継続的かつ安定的な実施の確保、事業の水準の維持 及び向上、司書及び司書補の確保並びに資質・能力の向上等が図られる よう、当該管理者との緊密な連携の下に、この基準に定められた事項が確実に実施されるよう努めるものとする」
この条文は、図書館を指定管理に委ねる場合の基準を定めたもの、と考えられます。末尾の「務めるものとする」とは努力義務で「実現できなければやむを得ない」と読み換えできる微妙な表現であり、実際、指定管理を導入した公立図書館の多くで「この基準に定められた事項が確実に実施され」てはいないことが明らかになっています。
このため、私たちは図書館の運営を指定管理に委ねることに反対です。次回は図書館を指定管理とすることの弊害について学習したい、と考えています。